公務員というと経済学部や法学部などの学生がなるイメージですが、理工学部の学生向けの職種も多くあります。
しかし、技術系の公務員になるにはどうすればいいのかイメージがわかない方も多くいると思います。

技術系の公務員に興味があるのですがどうすればなれますか?

私が実際に技術系の公務員に挑戦してきましたのでその体験を紹介します!
この記事では、学生時代に国家公務員総合職試験に挑戦した体験とそこから得た教訓を紹介します。
- 進路選択を控えた理工系の学生
- 公務員に興味がある学生
防衛省技術研究本部の見学会に参加
大学3年生も終わりに差し掛かり、2月下旬から春休みがスタートしました。
このくらいのタイミングで大学院に進学するか就職するかも決めることになりますが、私は大学院に進学するつもりでいました。
一方で、この時期から企業の採用活動も本格化しており、私も早めに情報収集をしておこうと思い、就職希望者向けの企業説明会にも多く参加するようにしていました。
そんな中、東京で防衛省技術研究本部(現防衛装備庁)の説明会が開催されるとの情報をネットで入手しました。
大学で船舶工学を学び、艦船マニアでもあった私は早速申し込んで参加することにしました。

説明会の情報は各省庁のホームページ等で確認しましょう!

技術開発官(船舶担当)(市ヶ谷)
市ヶ谷の防衛省の正門前に集合し、午前の部として技術開発官(船舶担当)の説明会に参加しました。

こちらは、海上自衛隊の艦艇の基本設計を行う部署で、技術系の海上自衛官や建造を行う民間企業と協力しながら、艦艇の仕様を決めたり基本的な設計を行う仕事になります。
感想としては、様々な関係者と協力しながらリーダー的なポジションで艦艇を構想をまとめていく仕事でとても魅力的に感じました。
艦艇装備研究所(恵比寿)
市ヶ谷での説明会の終了後、恵比寿に移動して、午後の部として艦艇装備研究所の見学会に参加しました。

こちらは、艦艇に関する要素技術を研究する部署で、船体性能や魚雷、電子機器など多岐にわたる研究分野を深く研究する仕事になります。
感想としては、全長約400mの巨大な試験水槽を始めとする様々な実験設備を備えており、規模の大きさに圧倒されました。また、設計というよりは研究がしたい人はこちらが向いていると感じました。
国家公務員総合職試験に挑戦
見学会を終えて、特に技術開発官(船舶担当)の仕事に興味を持ちました。
この仕事(艦艇装備研究所も同様)に就くためには以下の関門を突破する必要があります。
- 国家公務員総合職試験に合格する
- 官庁訪問(各官庁の選考)を受け希望する官庁の内定を獲る
このときが3月上旬で、国家公務員総合職試験は例年5月下旬からスタートするので、春休みを利用して国家公務員総合職試験に挑戦することにしました。
1回目の挑戦(大学3年終わりから4年初め)
国家公務員総合職試験の詳細は省略しますが、国家公務員総合職試験は一次試験と二次試験がそれぞれ別の日に行われます。

詳しい試験情報は人事院や公務員試験予備校のホームページ等で調べましょう!
専門試験は、文系科目や理系科目の中から自分の専攻に応じて区分を選択できますが、技術系の場合は多くの方が工学区分を選ぶことになると思います。
- 基礎能力試験
- 文章理解、数的推理、時事等
- 専門試験
- 工学区分の場合、材料力学、流体力学、電磁気学等(自分の専攻に応じて解く問題を選択可)
工学区分の専門試験の内容は院試に応用できる内容であるため、院試を受ける人であれば、大学3年終わりの春休みから専門試験の勉強を行っておけば院試の勉強において他の受験生をリードすることができます。
ちなみに総合職試験に合格すると、基本的には5年間の有効期間があります。
私も勉強の開始が3月中旬と遅かったのと、進路としては大学院に進むつもりだったので、修士1年で合格して、修士2年時に官庁訪問をすればよいと考えていました。
こうして総合職試験に挑戦することにした私は、院試の準備も兼ねて毎日大学の図書館に通って朝から夕方までできるだけ勉強しました。
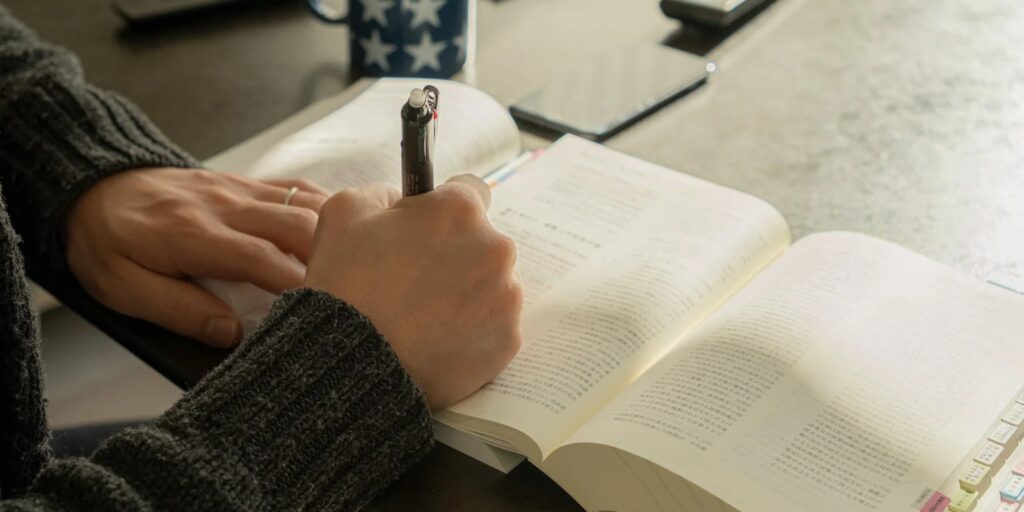
約2か月程勉強して、試験前日となりました。試験会場は遠かったので、会場近くのネットカフェに泊まり朝方まで勉強しました。

あまり褒められた勉強法ではありませんが、記念受験のつもりでそこまで深刻には考えていませんでした。
結局、寝不足と体調不良の状態で朝から夕方まで試験が行われてきつかったのですが、1回目の挑戦なのでそこまで気負わずに乗り越えました。
結果は一次試験不合格でした。
成績を見るとそこまで悪くはなかったので、来年挑戦すれば余裕で合格できるだろうと甘い見通しを立ててしまいました。
2回目の挑戦
1回目の挑戦の後も細々と勉強を続けました。
院試も難なく合格して進路も決まり、卒業研究も本格化して他のことを考える時間が増え、公務員試験の勉強をする時間はどんどん減っていきました。
その結果、学部卒業から院入学までの春休みになっても去年とあまり変わらない状況になってしまいました。
さらに悪いことに、春休みになっても勉強にあまり身が入りませんでした。
結局、一次試験を受けたものの午前の専門試験でボロボロになって不合格を確信しました。
そして、午後の試験をバックレて逃げ帰りました。
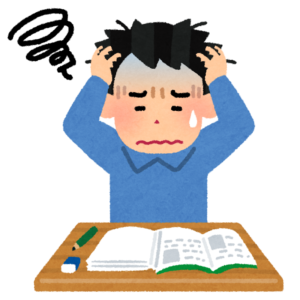
結局1回目よりひどい結果になってしまいました。
修士2年にもう一回チャンスがあるため、それまで再びだらだら勉強して修士2年の就活シーズンを迎えたました。しかし、勉強も進まず、民間企業が本命でその対策が疎かになるため、受験せずに撤退することを決めました。
こうして私の挑戦は不完全燃焼という形で終わりました。

「今回は記念受験で来年が本命」という考えは非常に危険だという教訓を得ました…。
公務員試験を通して得た教訓
最後に公務員試験に挑戦して得た教訓をまとめます。
時間対効果について考える
国家公務員総合職試験は数ある試験の中でもトップクラスの難関試験です。
したがって、十分な勉強量と勉強の質が求められます。
その時間があれば、学生の本分である研究で成果を出したり、長期インターンシップなどの課外活動に打ち込んだりして民間企業の選考でアピールできる経験を多く積めると思います。
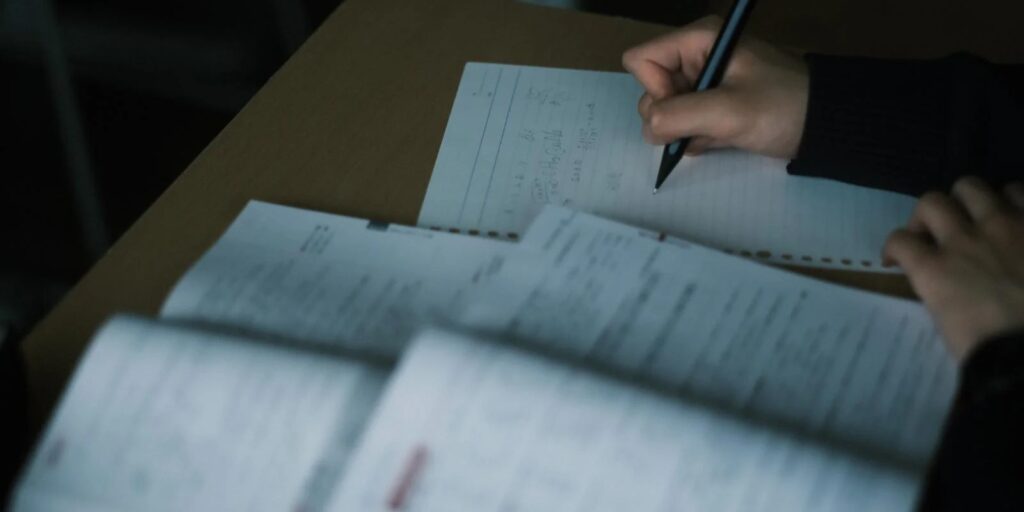
ちなみに大学3年次の進路相談で進路担当の教授に防衛省技術研究本部に興味があることを話したら次のようなことを言われました・
- 艦艇に関する研究力は技研より総合重工メーカーの方が高い。
- 公務員試験は成績が悪い学生が一発逆転を狙うために挑戦するもの。
- 成績がよいのであれば学校推薦で総合重工メーカーに就職するのがよいのでは。

ちょっと極端ですが、本質を突いていると思います。
研究力についてはっきりしたことはわかりませんが、三菱重工が基本設計案を提案した「もがみ型護衛艦」が量産されたり、JMUが基本設計案を提案した哨戒艦が量産予定であることなど、艦艇の基本設計における造船所側の発言力は高くなっていることは事実だと思います。
また、公務員の選考において筆記試験の重みが民間企業よりも高いことから、勉強による一発逆転を狙いやすいのも事実だと思います。
したがって、公務員試験でしか使えない勉強に学生生活の貴重な時間を注ぎ込むよりも研究、課外活動に力を入れた方が時間対効果が高いと思います。
受験するのであれば短期決戦
公務員になることが本命であるのであれば、公務員試験の勉強は短期決戦で行うべきだと思います。
総合職試験合格の有効期間は基本的に5年間なので、来年合格すればいいという考えは捨てて学年が若いうちにさっさと合格すべきです。
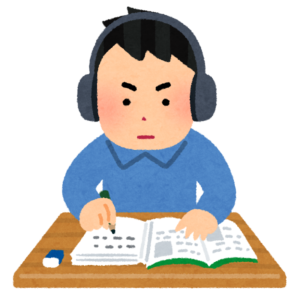
学年が上がるほど研究や就活で忙しくなるのでどんどん不利になっていきます。

この教訓はあらゆる試験に共通します!
公務員は厳しい階級社会
例えば、国家公務員の場合、入ったときの試験区分によって総合職(キャリア)と一般職(ノンキャリア)に分けられます。
例えば、防衛省で造船分野を担当する場合、総合職であれば、艦船の基本設計や研究といった業務を担当し、一般職の場合、基本的には総合職のサポートや定型業務を担当します。
総合職と一般職とでは、昇進スピードやキャリアパスにはっきりとした差がつけられています。
総合職で入ったとしても官僚の最高位である事務次官の椅子を巡って熾烈な競争が待っています。

その競争は出身大学や派閥など様々な要素が絡み合う古めかしいもので理不尽なことも受け入れなければなりません。
そして、年功序列である程度まで出世するもそれ以上出世できなかった者たちは早々に官庁を去り、民間企業等に再就職することになります。
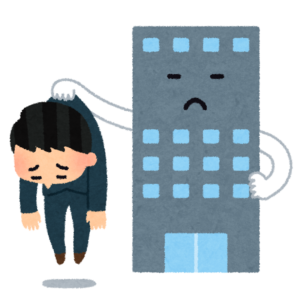
これが一般的に言う「天下り」です。
そういった古い組織体質が根強く残っている点は留意しておく必要があると思います。

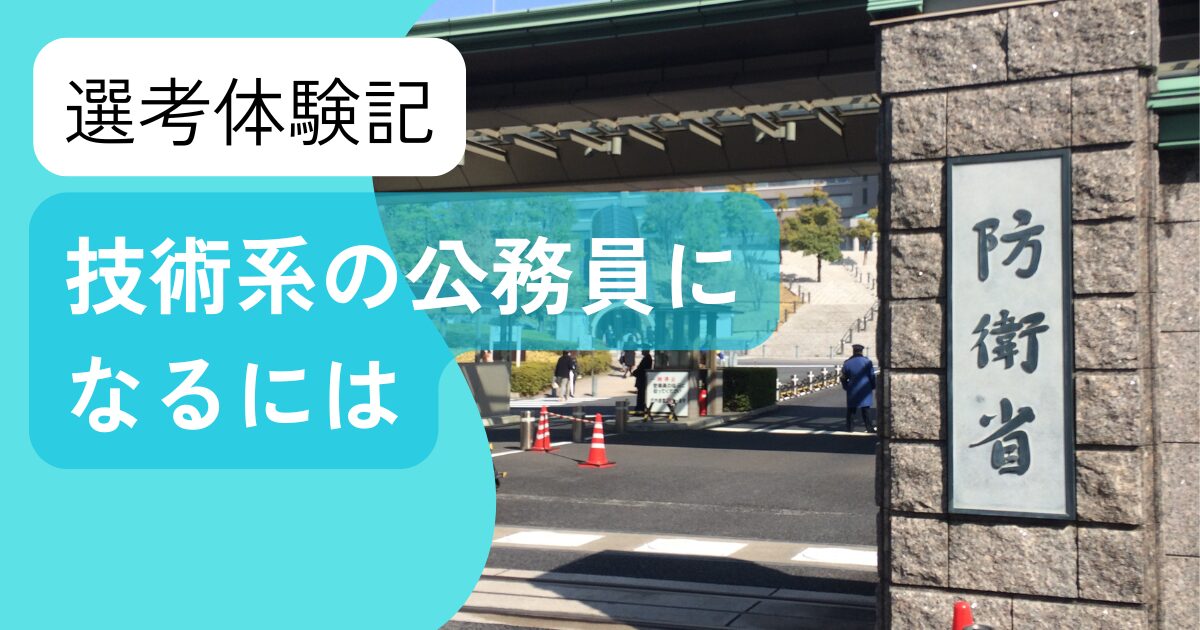

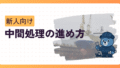
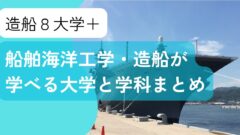
コメント