記事内に商品プロモーションを含む場合があります
転職活動の結果、めでたく転職先が決まって喜ぶのも束の間、次に向かって進むためにやらなければならないことが退職の手続きです。
初めて会社を辞める場合、切り出すのが怖くて不安な方も多いのではないでしょうか。

申し訳ない気持ちで退職を切り出すのがつらいです…。

今は転職が当たり前の時代で多くの人が乗り越えているので心配しなくて大丈夫です!
この記事では、過去3回の退職を経験した私がスムーズに円満退職するポイントと必要な手続きについて解説します。
退職は何カ月前に伝える?退職を伝えるタイミングについて
結論から言えば、退職を伝えるタイミングは会社の就業規則に則ったタイミングで伝えましょう。
会社によって退職を申し出るタイミングは退職日の1カ月前だったり、2か月前だったりと様々です。

法律的には退職の2週間前に伝えればいいのですが、トラブルになると必要な書類の入手や手続きがスムーズに進まなくなるので就業規則に従うのがベターです。
そもそも転職活動の時に転職先に入社日を伝える必要があるので、転職活動の段階で就業規則を確認してから入社日を決めておきましょう。
入社日は転職先と調整することになりますが、会社が希望する入社日は、月中の給与計算の締め日の翌日だったり、月初め初日だったりと様々です。
退職日の決め方と退職日によって必要な手続き
転職先が決まっている状況での退職の場合
転職活動の段階で就業規則に基づく期間を考慮して入社日を決めているので、できるだけ退職日は入社日の前日に設定するようにしましょう。
退職日と入社日との間に空白期間があると、個人で国民健康保険や国民年金への切り替え手続きと空白期間の分の費用を支払うことになり手間と費用が余分に発生します。
退職日と転職先への入社日との間に切れ目がなければ、転職先の指示に従って諸々の手続きをすれば問題ありません。
進学に伴う退職や転職先にすぐに入社しない退職の場合
事情によって退職日から次の会社に入るまで期間が空く場合は少し面倒な手続きが必要になります。
特に問題になるのは健康保険と年金です。
健康保険の手続き
健康保険については、退職した会社で入っていた健康保険を続ける任意継続を行うか、国民健康保険に加入するか、家族の健康保険に加入するか(被扶養者になる)を選択することになります。

一般的なメリットとデメリットをまとめると以下のようになります。

私の例では、会社を退職して大学編入したときは国民健康保険に加入して、会社を退職して2カ月後に特許事務所に入所したときは任意継続を選択しました!
| 選択肢 | メリット | デメリット | 適している人の例 |
|---|---|---|---|
| 任意継続被保険者 | – 会社員時代と同じ保険が使える(保険証の変更なし) – 保障内容が厚い | – 保険料が全額自己負担(会社負担分も含む) – 最長2年までしか継続できない | – 収入が高めで保障重視の人 – 短期間で転職予定の人 |
| 国民健康保険 | – 所得が少なければ保険料が安くなる可能性あり – 加入期間の制限がない | – 医療費の自己負担割合は同じだが、傷病手当金等の保障がない – 保険料計算が複雑になることも | – フリーランスになる人 – 無職期間が長引く可能性がある人 |
| 被扶養者になる | – 保険料の自己負担がゼロ – 家族の健康保険に入るだけで済む | – 年収130万円未満(※)などの条件を満たす必要あり – 審査に時間がかかることもある | – 配偶者などが会社員で条件を満たす人 |
年金の手続き
会社で厚生年金保険に加入していたと思いますが、退職後に空白期間ができる場合は、国民年金に加入するか、家族の被扶養者になるかを選択することになります。

通常、国民年金に加入することになりますが、退職日の翌日から14日以内に加入手続きを行う必要がありますので、速やかに手続きを行いましょう。
退職に伴って生じる支出
退職に伴って最後の給料から住民税や社会保険料が一括徴収されて手取りが大きく減るので注意が必要です。
住民税
- 住民税は前年の所得に基づいて課税される「後払い制」です。
- 通常、6月から翌年5月までの12カ月で分割して支払います。
- 会社員の場合は、給与から毎月天引き(特別徴収)されています。

転職して収入が下がったときに追い打ちをかけるように前年の所得に基づいた住民税が請求されるので嫌になります…。
| 退職月 | 住民税の支払い方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1月~5月 | 会社が一括で残りの住民税を天引き(一括徴収)するのが一般的 | 最終給与から複数月分がまとめて引かれるため、手取りが大幅に減ることがある |
| 6月~12月 | 通常どおり月ごとの天引きで終わる(未納分なし) | 退職後、翌年6月から普通徴収(自分で納付)に切り替わるため、注意が必要 |
社会保険料
- 社会保険料は「月単位」で発生。
- その月に1日でも社会保険に加入していれば、1カ月分の保険料が発生します。
- 支払うのは翌月の給与から天引きされることが多い。
社会保険料(健康保険+厚生年金保険)の負担額や加入状況がどう変わるのかは、退職日が月の「末日」か「途中」かによって大きく違ってきます。
| 退職日 | 社会保険料の扱い | ポイント |
|---|---|---|
| 月の途中 | その月の前月分までが対象 | 退職月分は支払わなくてよい |
| 月末(最終日) | その月の分まで支払う必要がある | 退職月もまるまる1カ月分の社会保険料がかかる |
例えば、3月15日に退職する場合は、2月分までが対象で3月分は徴収されません。
一方で、3月31日に退職する場合、2月分と3月分が対象になり2月分と3か月分が徴収されます。
月の途中での退職は得をしているように見えますが、国民健康保険、国民年金の負担は必要になるので、必ずしも得をするとは言い切れません。
退職の伝え方|退職理由の言い方やタイミングを解説
当たり前ですが、退職することを直属の上司に伝えるまでは決して同期や同僚に話したり、特定される恐れがあるSNSなど書き込まないようにしましょう。
上司に伝えるまでに噂になるとトラブルになって手続きが円滑に進まなくなります。
退職日から就業規則で定められた期間を逆算したタイミングで、直属の上司に退職の意思を伝えます。

会議室を確保して、業務相談という名目で上司と1対1の打合せを設定するとよいと思います。

打ち合わせを設定された時点で上司も察すると思います…。
「現職ではできない~の仕事に挑戦したい」などと前向きな理由と共に〇月〇日付で退職したいと伝えます。
当たり前ですが、何を言われても退職の意思は覆さないようにしましょう(ここで意思が揺らぐ程度の覚悟で転職活動を始めるべきではありません)。
上司に退職の意思を伝えたら、上司はさらに上の上司に相談して、さらに人事に話がいくという形で話は勝手に進んでいきます。
数日後には上司か所属長から退職届を書いて提出するように連絡がきます。
退職届の書き方
大きな会社の場合、退職届のフォーマットがあることが多くそのフォーマットに記入すれば問題ないです。
フォーマットがない場合は、便箋に自分で書くことになりますが、書き方は検索すればすぐ出てくるので割愛します。

定型文そのままで問題ありません!
退職理由は「一身上の都合により」と書けば十分でそれ以上は書く必要はありません。
退職届を書いたら封筒に入れて、他の人に気づかれないように上司にこっそり渡します。
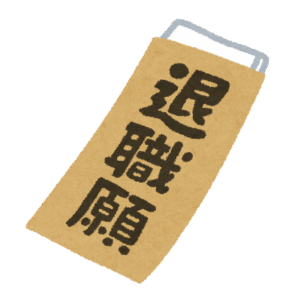
上司に伝えたとしても、会社から正式に発表されるまでは他の人に退職することを話すことは控えておきましょう。
退職までの流れ
退職届を上司に渡したら、また会社の方で勝手に手続きは進みます。
手続きが進むと次は上司と最終出勤日を調整します。
そして、最終出勤日から退職日までは有給消化期間となります。
多くの場合、最終出勤日が決まると会社から部署内に正式に退職が周知されるので、ここまできてやっと退職することを他の人に話してもよいことになります。

毎回、周りから「え!辞めるの!?」となります…。
最終出勤日までに引継ぎや残務処理を行っておきます。

必要な書類を請求するなど退職後も会社とやりとりする場合があるので、それらが円滑に進むように最後までしっかり仕事はしてトラブルにならないように気を付けましょう。

最初の退職の時は残務処理がかなりきつかったです…。
退職日が近くなったら挨拶周りもしておきましょう。
最終出勤日が近づくと、人事から案内が来て、必要な書類を受け取る手続きを行います。
退職時に会社からもらう書類
退職時に会社からもらう書類が基本的に以下の4つです。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
離職票
失業保険を申請するために必要な書類です。
転職先が決まっている状態での退職や進学に伴う退職の場合は失業保険の対象者には該当せず、基本的には必要ありません。
雇用保険被保険者証
失業保険の申請や転職先での雇用保険加入手続きに必要な書類です。
状況によらず必ずもらうようにしましょう。
年金手帳
国民年金への切り替えや転職先での厚生年金加入に必要な書類です。
原則本人が保管し、会社に預けていた場合は返却されるので所在をしっかり確認して、会社に預けている場合は必ず受け取りましょう。
源泉徴収票
年末調整や確定申告に必要な書類です。
転職の場合は、転職先での年末調整 進学の場合は確定申告で使います。
源泉徴収票の発行は退職後になるケースもありますが、いずれにしても必ず受け取りましょう。
最終出勤日の対応
最終出勤日は基本的に人事の方が対応してくれます。
必要な書類を受け取るとともに、貸与されていたパソコンや備品、社章等を返却します。

技術職の場合、社章をつける機会がほとんどなく無くしがちなので気をつけましょう!
最後に入館証を返却して会社に出れば退職完了です。
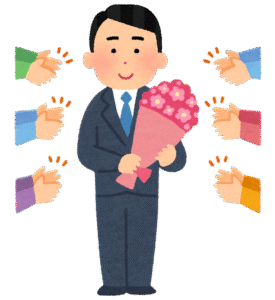

入館証を返すともう会社には入れないので退職したことを実感します…。
最後に、退職時には送別会があることが多いので楽しんで終わりましょう。
最近話題の退職代行について
退職までには何回も上司とやり取りしたり、退職することが周囲わかって気まずくなったりと、心理的、手続き的負担がかなりかかります。
だからといって、安易に退職代行を使うのはやめておきましょう。
業界内は思っている以上に狭く、業界内の人事同士の繋がりを通じて、退職代行を使ったという噂が広がりかねないからです。

退職代行は、あくまでも、パワハラによって心身が限界に近い状態だったり、退職させないように脅迫されたり、通常の退職手続きが自分で行えない事情がある場合の最終手段と考えておきましょう。
まとめ
以上、退職手続きの流れとポイントについて解説しました。
再度、ポイントをまとめておきます。
- 就業規則を考慮して入社日と退職日を決定
- 退職の意思は直属の上司に伝え、正式発表までは他言しない。
- 健康保険と年金の手続きに注意
- 必要な書類を会社から漏れなく受け取る
転職が当たり前の時代なので、きちんとした手順を踏んで手続きすればトラブルなく辞めることができます。
この記事を参考に円満退職して気持ちよく次の道に進んでいただけたらと思います。

私は退職前にメジャーなテキストを一冊買って準備しました!



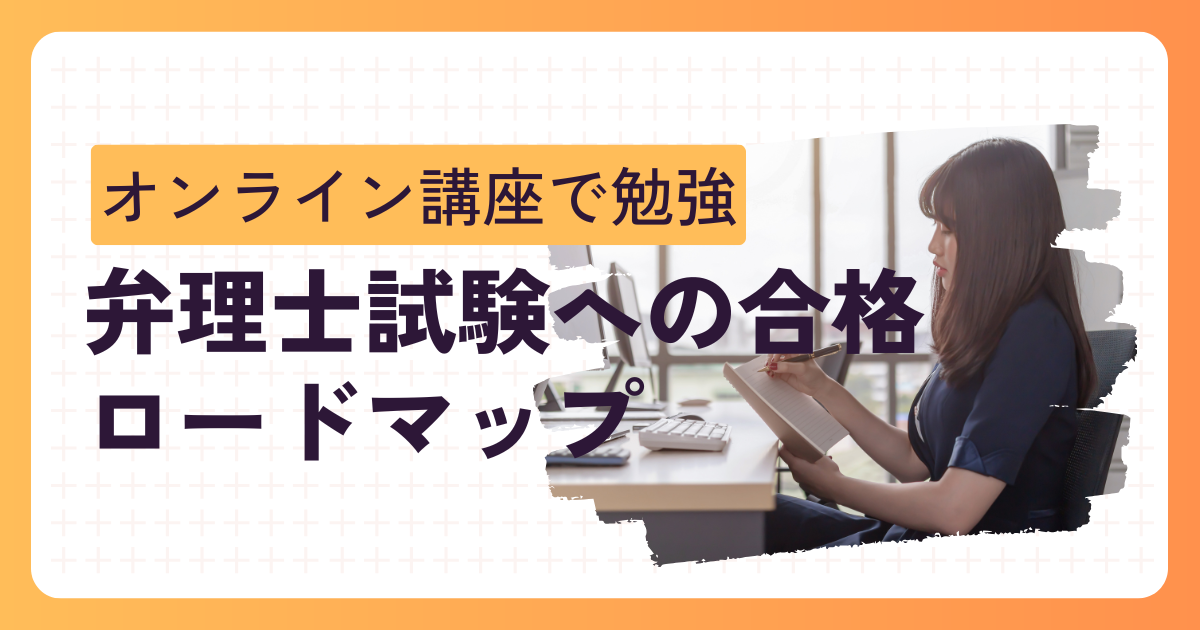
コメント