記事内に商品プロモーションを含む場合があります
めでたく論文試験に合格できましたら、最終合格まであと一歩です!
しかしながら、最後の関門として口述試験が待ち構えています。
口述試験の合格率は9割程と高いのですが、合格基準に達しないと普通に落ちるのと、残された期間が1カ月とないので、このラストスパートはかなりきついものになります。

論文合格しました!口述まで残り1カ月しかないのですが対策はどうすればいいですか?

口述試験までにするべきことをまとめましたので参考にしてください!
この記事では、口述試験までに「これをやれば合格できる!」という勉強法を紹介していきます!
口述試験の概要を確認!
試験会場と日時
会場は例年、東京にある「ザ・プリンス パークタワー東京」で行われています。

弁理士界隈ではラスボスタワーと呼ばれていますが、超高級ホテルです!
下の写真の左側の建物で東京タワーの近くです。写真手前の芝公園からアクセスできます。

試験日時は、例年、10月中旬から下旬の土日に行われます。
そして、土日のいずれかの日、さらに午前と午後のいずれか時間に振り分けられます。

東京から遠い人ほど移動を考慮して遅い日程に振り分けられがちです。
口述試験の試験内容
出題科目は、特実、意匠、商標の3つで、試験時間は各科目10分ずつです。
評価はA,B,Cの3段階で2科目以上でC評価となると不合格となります。
最後の問題の解答まで時間内に終わらないとC評価となってしまいます。

試験時間内に最後の問題まで辿り着くことが重要です!
口頭だけで問われる問題だけではなく、各科目それぞれ、事例を図示したパネルに沿って出題されるパネル問題もあって、苦手意識を持つ受験生は多いと思います。
なお、試験用法文が貸与され試験官の許可を得て参照することができます。
口述試験の対策まとめ
口述練習会を最速で予約!
論文試験に合格したら直ぐに資格予備校や各弁理士クラブの口述練習会を予約します。
枠が限られていてすぐに埋まってしまうので早めに情報を入手し受付開始とともに直ぐに予約しましょう。
特にLECとTACの口述模試は模試の後にもらえる冊子が超重要ですので必ず両方受けておきましょう!
LECとTACの口述模試は、例年、10月初旬から中旬に行われます。

私は、10月10日の午前にLEC、午後にTACの模試を入れました!
口述模試は東京と大阪でしか受けられませんがラストスパートなのでここで交通費を惜しんではいけません。

私は夜行バスで大阪に模試を受けに行ってその日に再び夜行バスで帰ったのできつかったです…。
各弁理士クラブの練習会ですが、対面だったりオンラインだったり練習形式は様々です。スケジュールの許す限りできるだけ受けておいた方がいいです。
私は受けていませんが、春秋会の模試は本番と同じ「ザ・プリンス パークタワー東京」で行われます!

私は地方なのでオンラインで参加できる下記の模試に参加しました。
| PA会口述練習会 | Zoomによる練習会です。難易度としてはLECやTACの模試と同様かと思います。本番1回分の練習ができます。 |
| 南甲弁理士クラブ口述練習会 | GATHER(バーチャルオフィス)による練習会です。ドラクエのような画面でキャラを操作して特実、意匠、商標ブースを移動します。各ブースでZoomのような形式で練習します。本番2回分の練習ができます。 |
| 西弁・口述ウェブ模試 | Zoomによる練習会です。難易度は高めですがその分鍛えられます。本番1回分の練習ができます。 |
論文合格から10月初旬(資格予備校の模試まで)にかけてやるべきこと
先ずは、資格予備校の口述模試に向けて口頭で回答する練習を始めましょう。
ここで使う口述試験のテキストですがLECの口述アドヴァンスドテキスト(以下、口アド)一択です。

口アドはLECから購入できます!
また、この段階までくれば青本を直接読んでも理解できると思いますので補助的に青本の読み込みもしておきます。
勉強方法としては、家族や受験仲間に協力してもらって問題を口頭で読んでもらい、口頭で回答する練習をしておきます。

私も毎日、妻と1時間程度練習をしました。
また、1人で口アドを読むときも、自分の口で諳んじるようにします。
ちょうど涼しくもなってきた頃なので、机について勉強するというよりは、外に出て秋を感じながら練習すると気持ちがよいですし、記憶や話す能力として定着しやすいと思います。

テキスト片手にブツブツ言いながら公園を歩く姿は完全に不審者なのですが気にしてはいけません!
とにかく、口と体を動かしながら口アドの回答を反射的に自分の口と言葉で言えるように繰り返し練習しましょう。
資格予備校の口述練習模試後から試験本番にかけて
口アドに加えてLECとTACの口述模試後に貰える冊子についても、口アドと同様に自分の口で言えるように訓練します。
ただし、これだけでは知識と知識の間にスキマができるので、このスキマは青本の読み込みで埋めるよにします。
さらに、申し込んでおいた各弁理士クラブの模試が始まってきますので、実際にアウトプットしながら本番に向けた調整を進めておきます。
余裕があれば、下記のテキストでさらに多くの出題パターンに触れておきましょう。
試験本番の流れとポイント
会場での流れ
指定された時間にホテルの1階の集合場所に集合したら、会場とおなじフロアにある控室に通されます。
控室になるホテルの部屋には椅子が規則正しく並べられていて、椅子に座って順番を待ちます。
控室の雰囲気は下の絵のようなイメージです。

座る順番と呼ばれる順番は関係はないです。
待ち時間がかなり長く、いつ呼ばれてもおかしくない緊張状態の中で待たされるのでかなりつらいです。
試験官に言えばトイレに行かせてもらえますし、参考書も読めますが、スマホ等の通信機器は封筒に入れて封印されるので使用はできません。
呼ばれたら試験室前の廊下に並べられた椅子で少し待ちます。
そしていよいよ試験室です。雰囲気は下の絵のようなイメージです。

特実の部屋、意匠の部屋、商標の部屋の3部屋が隣り合っていて、それぞれ主査と副査の2人の試験官が待っています。
回答のポイント
躊躇せずに条文を参照
宙で答えきれないと感じたときは、迷わず「試験法文を参照してよろしいでしょうか?」と承諾を得てから、条文に沿って回答しましょう。
その方が正確に解答できて話が早く進み、制限時間内に回答しきることに繋がります。
話を繋げて助け舟に乗る
問題の途中で回答が出てこずに詰まってしまうことがあると思います。
そんなときでも決して沈黙せずに何か話すようにしましょう。
そうすれば、試験官が助け舟(回答にたどり着くためのヒント)を出してくれることがありますので、助け舟に乗って回答を進めていきましょう。
聞かれていることに端的に答える
口述試験は試験官との対話です。
聞かれていることに端的に答え、余計な事まで一方的に話さないように気をつけましょう。
回答が不足していれば試験官から追加で質問してくれますので、回答は小出しにすることを意識するとよいと思います。
やっぱり基本的なマナーや姿勢は大事!
最後に、試験官は敵ではありませんし、基本的には合格させてあげたいと思っているはずです。
基本的なマナーがなってなかったり、横柄な態度では助け舟も出してもらえなくなります。
企業の面接を受けるつもりの服装と態度で臨むようにしましょう。
最後に
口述試験では実際に受験した感触で合否が大体わかると思います。

私は特実、意匠は雑談まで進んだ(商標は時間ギリギリ)ので合格を確信することができました!
いい気分で家路につけるように、残された期間全力で勉強し尽くしましょう!
この記事を読まれた方の最終合格を祈念しております。

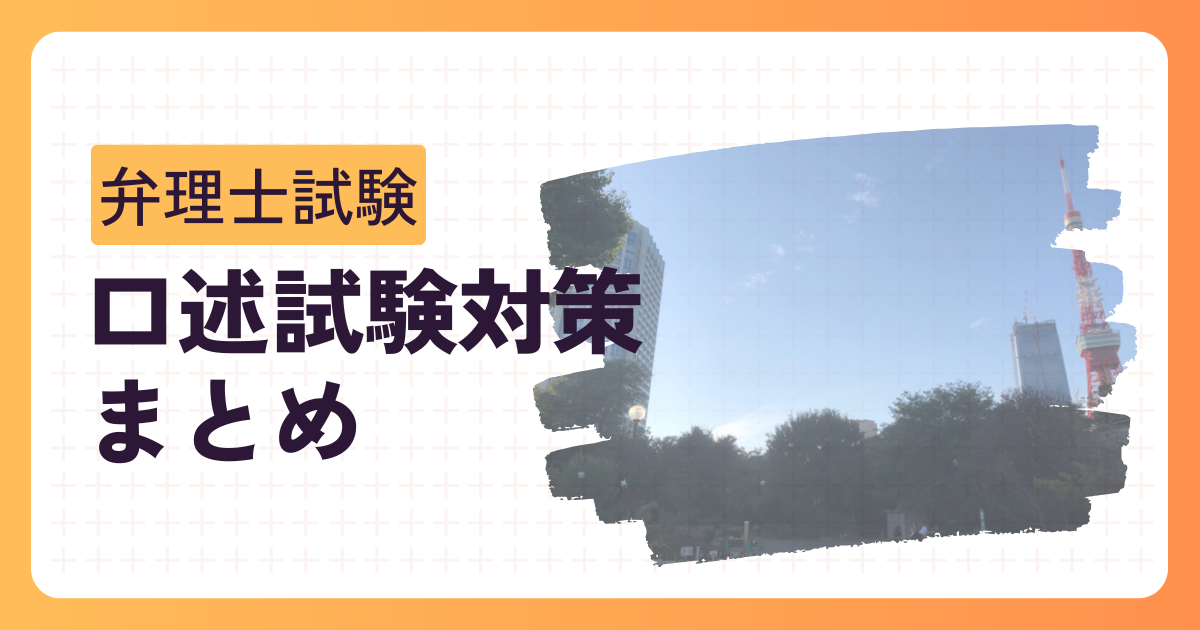
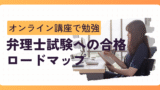
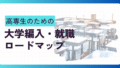
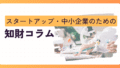
コメント